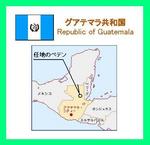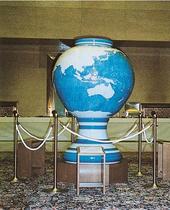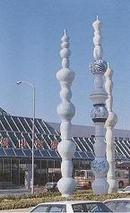1月6日午後、この度 日系社会青年ボランティアとしてメキシコに派遣される松山市の藤岡さんと同行し、愛媛県庁では夏井幹夫企画情報部長を、松山市役所では中村時広市長を表敬訪問しました。
1月6日午後、この度 日系社会青年ボランティアとしてメキシコに派遣される松山市の藤岡さんと同行し、愛媛県庁では夏井幹夫企画情報部長を、松山市役所では中村時広市長を表敬訪問しました。
『日系社会青年ボランティア』とは、青年海外協力隊と同じJICA(独立行政法人国際協力機構・理事長 緒方貞子)の国際ボランティア事業であり、中南米地域の日系社会で、自分の持っている技術や経験を活かそうという青年を派遣し、支援するのが日系社会青年ボランティア事業です。日系社会青年ボランティアは、移住者・日系人の人々とともに、生活・協働しながら、中南米の地域社会の発展のために協力をするボランティアであります。
今回派遣される藤岡さんは、メキシコのメヒカリ市の語学センターで日本語学校の講師として2年間派遣されます。既にメヒカリ市の同センターでは日本語教育を行う学校として基盤は整い、生徒数も増加していますが、日本語を十分に話せる日系人が既にいなくなっているので、学校で日本語クラスの担当教師、また日本語教師への指導、日本文化の紹介を目的とした行事の企画、実施などがこの度の派遣目的であります。彼女はこの学校では歴代5代目の先生になるとのことです。
愛媛県から日系社会青年ボランティアとして派遣されるのは、藤岡さんが8人目となります。
藤岡さんは、大学でスペイン語を専攻し、学生時代にメキシコには2回の訪問滞在があり、それがご縁となり今回のメキシコ派遣に繋がったとのことでした。メヒカリ市は、メキシコの北部のアメリカとの国境近くに位置し、太平洋に面した街で人口は80万人とのことです。夏は40度を超える暑さになるとのことでした。対日感情も良いところであるとのことであります。今月の13日にメキシコへ向けて出発されます。
夏井企画情報部長からは、「派遣中、身体には十分お気をつけ、元気に帰ってきて欲しい。またその経験を愛媛で生かして頂けるよう期待している」との激励の言葉がありました。
写真は左から
【夏井幹夫企画情報部長と懇談されている藤岡さん】
【育てる会の運営委員長(戒能潤之介県議)と藤岡さんと私】
【今回同行のJICA、育てる会のメンバーと中村時広市長、藤岡さん】
【夏井幹夫企画情報部長と懇談されている帰国隊員4人】
続きを読む "『日系社会青年ボランティア』の出発前の表敬訪問に同行しました。" »